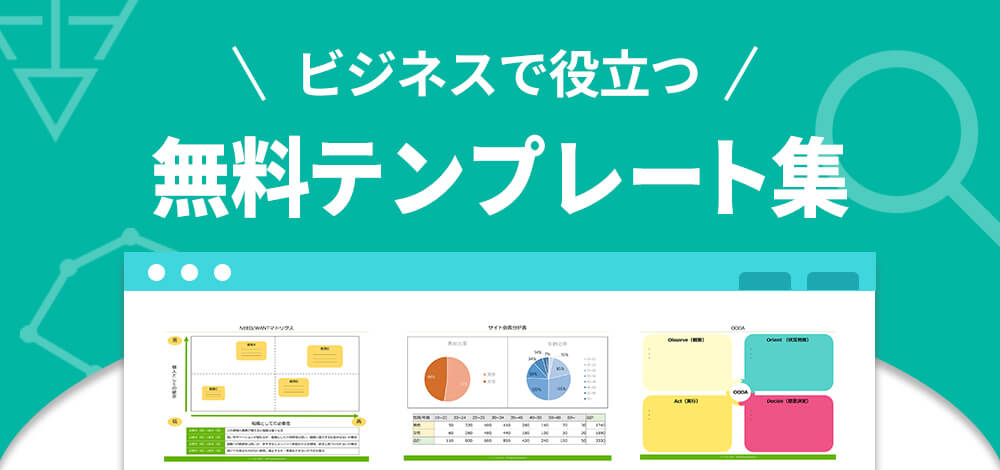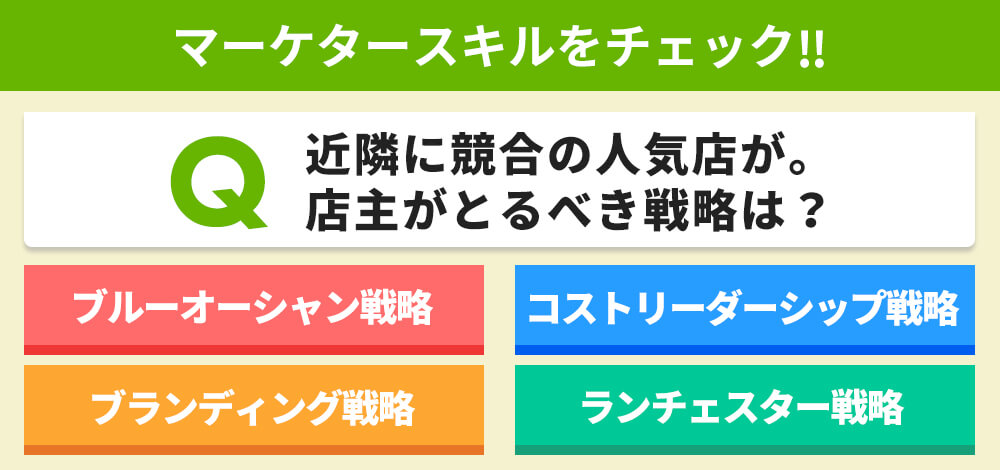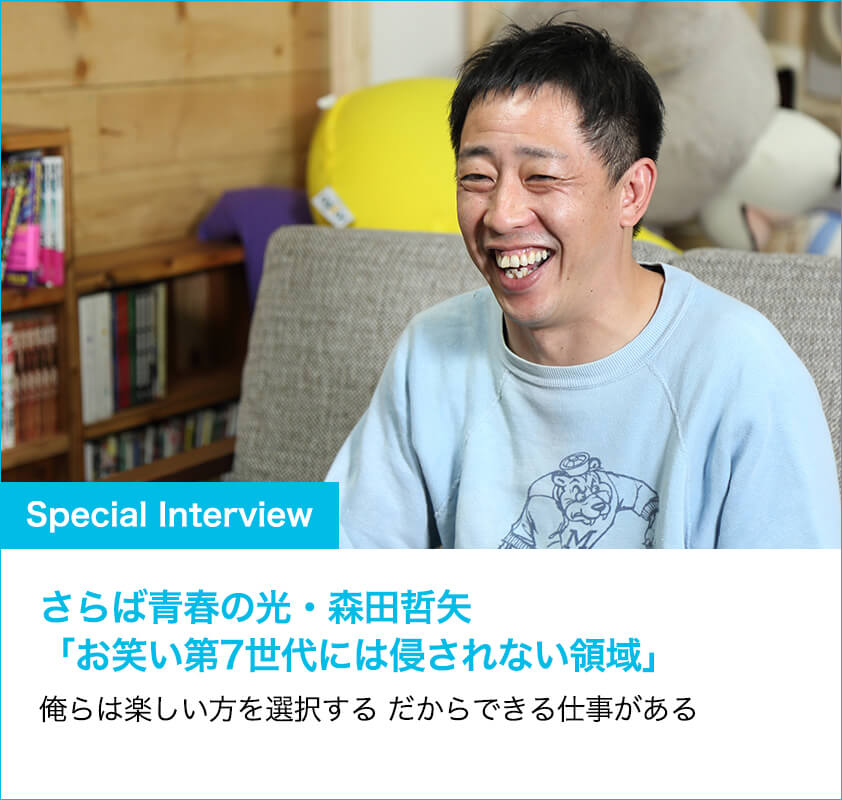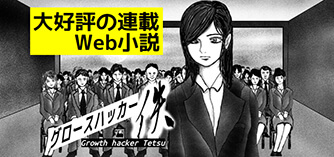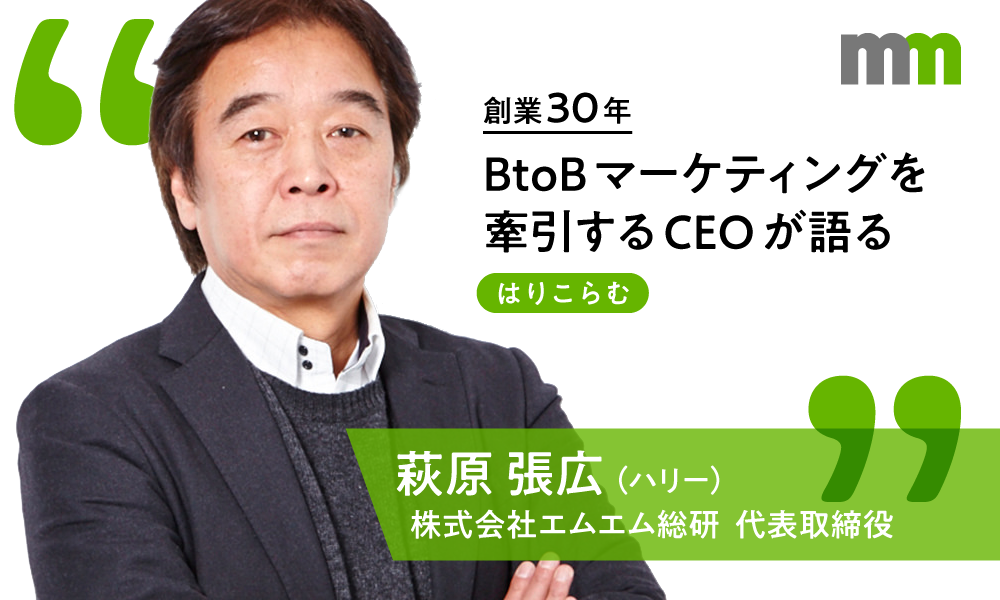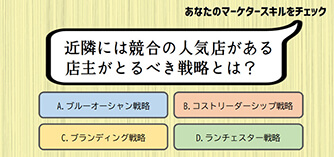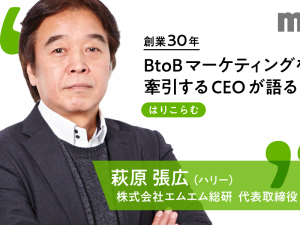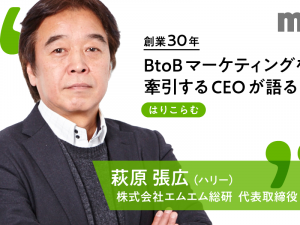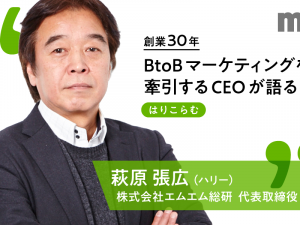営業力という言葉にどんなイメージを持ちますか?20年ほど前、最初に出版した「営業の科学」~根性主義でない普通の人間がやれる営業の法則~(ダイヤモンド社)で、私自身の経験を題材に営業力を因数分解する内容を書きました。
高校卒業後、技術系の会社に就職しましたが半年で退職、もう後がない状況で始めたのが営業の仕事でした。 最初は英会話教材の営業で、個人宅に電話してお客様に喫茶店に来ていただき、その場でクロージングする営業です。英語を話したい人は多いので、多くの人が営業対象になります。当初、街を歩いている人が全部お客様候補に見えました。実際、電車の中で辞書を引きながら英語の雑誌を読んでいる女子大生に声をかけて、喫茶店に連れて行ってプレゼンしたこともありました。今ではちょっと考えられないですね。
潜在ニーズ的な人に営業するので、啓蒙的な営業力が必要で人によって受注率はかなり差が出ました。考える時間を与えるとまず買わないので、即決を迫るクロージング力も必要です。私自身必死に一人暮らしのアパートで毎晩夜中まで一人ロープレしてトーク技術を磨き、一時はクロージング率が70%を超えるまでになりました。でも買った後に実際英会話の教材を使っていなかった人も多かったと思います。善悪は別にして業績的にはとにかく売ってしまうことが重要でした。お客様のことを考えると言うよりは、自分や自社の業績貢献というのが営業の目的になっていたと思います。
その後転職して、建築資材の営業になりました。 こちらは、タイル工事屋さんに材料となるタイルや風呂釜を売る仕事です。お客様から見れば商売の仕入れになります。
当たり前ですが、実際の工事に使わないものは営業しても買いません。英会話教材の様に啓蒙する様な営業力は必要ありません。むしろ期待させる様なトークを使うと勘違いされて、後で問題になることも多いです。英会話教材の癖が抜けず、最初は苦労しました。一方、同じ材料を買える建築資材商社は他にもあるので、商品での差別化は難しいです。また工事材料の仕入れですから、ずっと取引は続きます。
そうなるとお客様との関係性や信頼関係がとても重要です。接待もありました。その会社は、「お客様は神様です」と経営理念にも書いていました。会社の業績の為に無理やりお客様に合わせるとか、いろいろな要望にも我慢すると言う感じだったと思います。お客様は神様ですと言いつつ、社内業績視点であることには変わりがなかったような気がします。
英会話教材などのハード的な商品を売り切る、また建築資材の様に差別化の効かない商品を関係性で売る。こういったパターンの営業は、昭和の高度経済成長時代には一般的でしたし、 またそこでの成功体験で培われた営業文化は今も日本には残っているかと思います。私個人的には業績は上げていましたが、「本当にお客様のためになっているのか?」「やっていて自分自身が楽しいのか?」などに疑問を持っていました。
そういった経験から、今のエムエムのトリプルウィン(営業従事者、 お客様、会社がそれぞれウィンな関係を構築して持続的な成長を目指す) という経営目的が生まれてきました。
多くの事業がサービス業化する中で、CS(顧客満足度)CS(カスタマーサクセス)の様な概念も言われるようになりました。 BtoBにおいては継続的な取引も前提の場合が多いので、LTV(顧客生涯価値)という概念もよく使われるようになりました。日本においても実際サービスの提供現場については、顧客貢献が評価される仕組みも出来てきていると思います。一方、営業現場だけは、依然として業績貢献視点での社内評価が中心かと思います。
今後AIが普及することにより、 日本においての営業のあり方自体に変革が訪れると考えています。その商品サービスを購入してウィンになれる可能性のある見込み顧客を探し、 適正にコミュニケーションして商談化までを担うマーケティングとインサイドセールス、そして契約後のお客様を成功に導くカスタマーサクセス。営業プロセスの多くはこの二つになりAIの活用などで標準化、生産性向上が実現されると思います。
営業としての仕事は、既存顧客のアカウント対応、 関連キーパーソンとの連携、そして契約業務(認識違いがなく、継続性のある契約の実現)を中心に、領域としては狭く一方内容的には深くなっていく。
業績視点においてもLTVの最大化を重要視するのであれば、営業現場も顧客貢献視点に思い切り変化する必要があるのではと思います。売るのではなく、購買支援の立場に立つことだと思います。
SNSやネットの広告には今でも「営業力の向上!」などをキーワードに使ったものがよくあります。何かまだ古い昭和の時代の表現だなと感じてしまいます。「現状の日本における自社の営業力とは何か」が言語化出来ていることが重要で、そこが分かっていないと間違った選択をすることも多くなるかと思います。
⇒次の記事はこちらから

■萩原 張広 Profile
株式会社エムエム総研代表取締役CEO。株式会社リクルートにて法人営業、営業マネージャーとして7年のキャリアを経て、株式会社エムエム総研を設立。法人営業のコンサルティングサービスを大手IT企業やベンチャー企業に向けて多数提供。1998年、ニューヨークでの視察経験から日本でのBtoBマーケティングの必要性と可能性を感じ、業態をBtoBマーケティングエージェンシーとする。以降、数百件のマーケティングプロジェクトに関わる。
 営業力という言葉にどんなイメージを持ちますか?20年ほど前、最初に出版した「営業の科学」~根性主義でない普通の人間がやれる営業の法則~(ダイヤモンド社)で、私自身の経験を題材に営業力を因数分解する内容を書きました。
営業力という言葉にどんなイメージを持ちますか?20年ほど前、最初に出版した「営業の科学」~根性主義でない普通の人間がやれる営業の法則~(ダイヤモンド社)で、私自身の経験を題材に営業力を因数分解する内容を書きました。