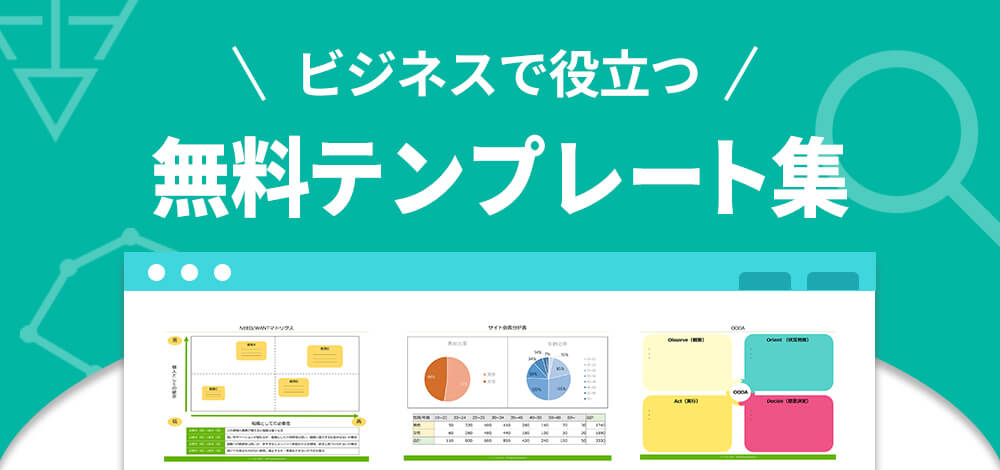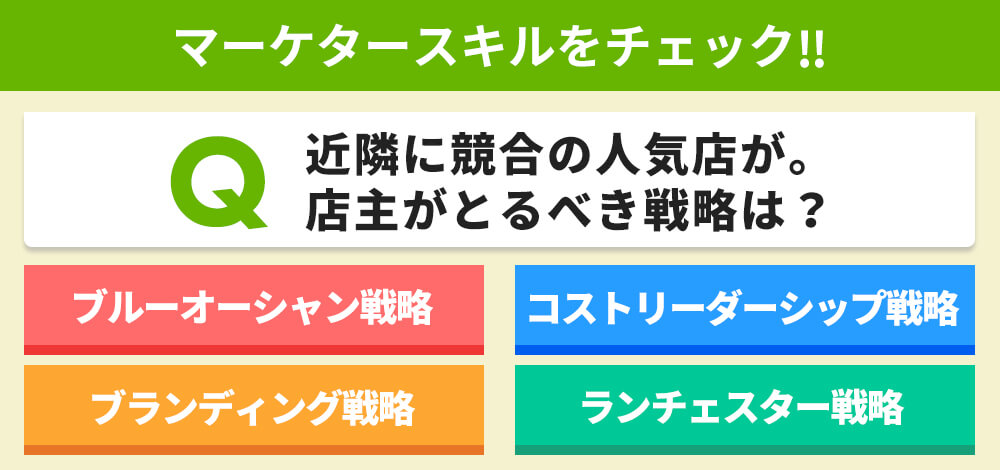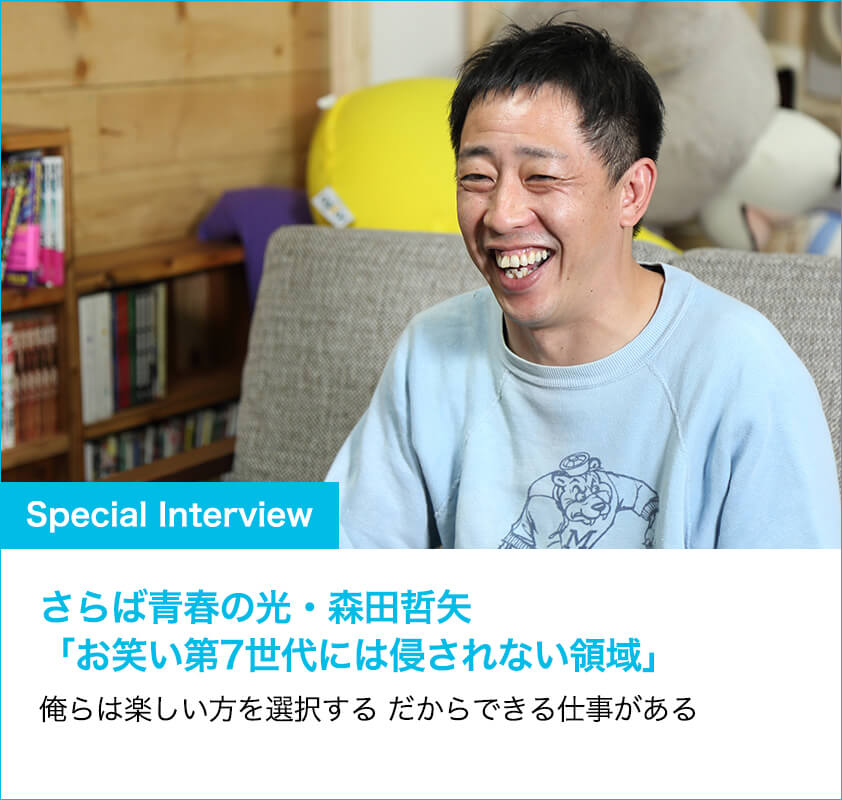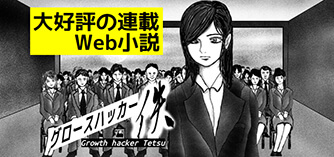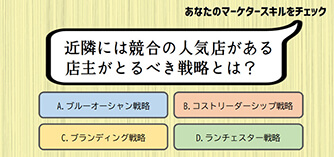この記事では以下のことが分かります。
・営業が苦情やクレームをうけるパターン
・苦情やクレームを受けたときの対応策
・そもそも苦情やクレームを減らすためにできること
営業へ苦情やクレームが発生するパターンと理由
BtoB企業でもBtoC企業でも、営業職は顧客に自社の商品を買ってもらうのが仕事。そのため営業と顧客との距離は他部署と比べるとずっと近いです。営業へのクレームは、営業がアプローチをかけたことによるクレームと、受注後のクレームに分けられます。前者は「営業電話がしつこい」のようなもの、受注後のクレームは「説明と話が違う」といったタイプが多いです。 それではどのような理由で営業へクレームが発生するのか具体的に見ていきましょう。
営業担当や会社に責任があるミス
クレームには、一度のミスで起こる場合と繰り返しミスが発生して我慢の限界を迎えて起きる場合があります。営業担当や会社に明らかな非がある場合は、クレームが発生しても仕方ないでしょう。たとえば「もう営業のための電話や訪問はしないでほしい」という話が以前にあったのにきちんと共有されておらず、知らずに営業をかけてしまってクレームが発生する、複数の営業担当が営業をかけてしまうといった営業活動自体へのクレームというのがこのパターンに該当します。これは、部署内できちんと情報共有できていれば防げるものですので、システムがきちんとあれば減らせます。
注意しなければならないのは、受注後のやり取りが原因でクレームや苦情が発生してしまうことです。営業担当は契約を取ることが仕事です。月単位の数値目標もありますので、契約後のフォローまで手が回らないことがあります。契約をした途端に急にフォローがなくなったとなれば、顧客はよい気分ではないでしょう。たとえ繰り返し受注をもらうような業種でなくても、顧客と長期的に良い関係を築くことは非常に重要です。営業担当だけで受注後フォローが難しいようなら、アフターフォロー専門の部署を利用するといった工夫が必要です。
相手の勘違い
これは自分のミスで発生するものではなく、顧客のミスや勘違いがきっかけでクレームに発展するというもの。きちんと文書と口頭で伝えているのに、相手が勘違いしているというパターンです。きちんと伝えているのならこちらに非はありませんが、相手に誤解を与えるような言い方をしている場合や、相手の知識不足で誤解しても仕方がないという場合も多いです。いわゆるその道の専門家である営業担当と、顧客では元々の知識量が違います。前提として、相手に分かりやすい説明ができているかどうかは常に気を配る必要があるでしょう。
お互いの認識のズレ
これはいわゆる「言った言わない」の問題ではなく、相手の理解と営業担当の理解が異なることで起きるものです。たとえばクライアントが営業に丸投げし、営業担当もきちんと相手に確認がとれない状況で、途中で相手から「思っていたのと違う」といった苦情が寄せられるパターンがこれに該当します。
相手が怒ることだけがクレームじゃない
クレームと聞くと、クライアントが会社に対して電話口で怒鳴っているといった光景が思い浮かぶかもしれませんが、ひとくちにクレームといっても相手の苦情の出し方はさまざまです。
感情が表に出ているタイプ
大きな声で怒鳴るようなクレームはこのタイプです。怒っているときは相手にまだ期待する感情が残ってとき。感情にまかせて苦情を言うタイプのお客様は、きちんとした解決策を提示し、その解決方法に満足してもらえれば引き続き契約をしてくれたり、新たな発注をしてくれたりする方が多いです。
論理的な苦情タイプ
感情を出すことなく根拠をもとに論理的に主張を述べるタイプのことです。怒りに任せて話すわけではないので、いわゆる話し合いがしやすいクレームとなります。基本的にはメリットやデメリットを重視する傾向のお客様なので、一度ミスをするとあっさりと契約解消になることが多いです。このようなお客様のクレーム対応をする際は、単なる謝罪だけでなく「今後も取引をするメリット」の提示が重要になります。
静かな怒りタイプ
こちらの不手際に対して「こうしてほしい」といった主張をするのではなく、淡々と事実だけを伝えるタイプのクレームです。クレームという形にならないことも多いですが、自社に非がある場合は対応が必要になります。
苦情やクレームを受けたときの対応策
人は誰でもミスや勘違いをします。そのため完全に苦情やクレームをなくすことは難しいです。ここではクレームを受けたときにどのような対応をすべきか、注意点とともに解説します。
まずは謝罪する
事実確認をしておらず、こちらに非があるかも分からない段階で謝罪をすることに違和感を持つ方もいるかもしれません。ここでの謝罪は、ミスや不手際があったことではなく、理由はなんにせよ相手の気持ちを害してしまったことへの謝罪です。
怒るのにはエネルギーが必要です。わざわざクレームを入れなくても、契約を解除すればそれで済むのにも関わらず時間を作ってクレームを入れているわけですので、まずは相手が怒っていることを理解し、謝りましょう。実際に自分のミスがあったかはこの段階では重要ではありません。言い訳をせずに誠実に対応しましょう。
相手の主張を聞き、整理する
感情を爆発させるクレームの場合は、相手の主張が二転三転したり、まとまっていなかったりすることが多いです。まずはお客様が何に怒っているのかをじっくりと確認しましょう。この段階で重要となるのは相手の話をじっくりと聞くこと。思うことがあっても途中で口をはさむことなくしっかりと聞いて、相手の主張が何なのかを分かるような質問を投げかけるようにしましょう。
事実を確認する
クレームは往々にしてお客様の主観が大いに含まれています。実際に起こったことと、お客様の主張は必ずしも一致しないでしょう。事実とお客様の主張を区別することで、実際はお客様の勘違いだと判明したり、すぐに解決できる内容だと分かったりします。
事実に対してどう対応するかを伝える
もらったクレームに対して自社に非があれば、当然それなりの対応が必要になります。ここで重要となるのは、冷静に判断すること。自身が管理職や責任者でなければ、上長に相談するようにしましょう。自身の判断で勝手な約束をしてしまうと新たなクレームを生むことになりかねません。クレームを言うお客様は、クレームを言うことが目的ではなく、会社や担当者への要望があるはずです。それに対して会社としてどうするか、相手の納得がいくように対応しなければなりません。
苦情やクレームを減らすためにできること
苦情やクレームをゼロにすることはできなくても、減らすことはできます。 まず意識すべきことは、クレームが出ないようにすることは顧客満足度を高めることだということ。クレームが出たときの対応も大事ですが、細かなところまできちんと確認しておけば、防げるクレームは多いです。顧客の小さなサインを見逃さず、また自身の経験だけを過信せず、相手との信頼関係を築くようにしましょう。