この記事では「デジタルトランスフォーメーションとは何か」から、実際のデジタルトランスフォーメーションの成功事例まで詳しく解説しています。デジタルトランスフォーメーションには、単なるデジタル化というイメージがある方も多いでしょうが、実際にはそれでは不十分です。基礎的なところからしっかりと解説していますのでぜひ参考にしてください。
デジタルトランスフォーメーションとは
デジタルトランスフォーメーション(DX:Digital Transformation)は、2004年にスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱されました。DTではなくDXと略すのは、英語圏では「trans」を「X」と略すことに由来しています。デジタルトランスフォーメーションとは何かについて、経済産業省では以下のように定義しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
つまりは製品をデジタル化するといった取り組みではなく、「デジタルを使ってビジネスモデルに変革を起こすこと」と言えます。当然ビジネスとは企業や一般消費者に向けて行うものですので、企業内だけでなく社会全体に変革が起きることになります。
経済産業省がデジタルトランスフォーメーションの推進についての具体的方策を盛り込んだガイドラインを発表するほど、デジタルトランスフォーメーションは現在注目を集めているものです。デジタルトランスフォーメーションへのよくある誤解としては「デジタル化=デジタルトランスフォーメーション」というものです。環境の変化に適応するための手段としてデジタルのテクノロジーやツール、データを活用することがデジタルトランスフォーメーションの本質です。デジタル化はあくまで1つの手段、ステップにすぎません。この点についてはしっかりと頭に入れておいてください。
たとえばオンライン商談ツールやWeb会議を導入するといったことは商談をデジタル化、会議をデジタル化しただけであってデジタルトランスフォーメーションではありません。現代では新たなデジタル技術を利用したこれまでにないビジネスモデルがどんどんと生まれてきています。時代の変化につれてビジネスモデルの展開方法も変化し新規参入企業が増えてきています。
そのような状況の中で既存の企業が収益を上げ続けるためには、これまで通りのやり方では難しく、場合によっては業務全体の抜本的な改革が必要となります。 業務全体の抜本的な改革として求められるのがデジタルトランスフォーメーションを進めることです。競争力を維持するためには従来通りのやり方では革新的な新規参入企業に太刀打ちできません。
デジタルトランスフォーメーションを進めることは競争上の優位性を保つために避けては通れないものなのです。つまりデジタルトランスフォーメーションは、「やるかやらないか」といった判断が求められるものではなく、「やらざるを得ないもの」と捉えるべきだと言えます。
デジタルトランスフォーメーションへの3ステップ
デジタルトランスフォーメーションへ至るまでには「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」の2つのステップを経ることになります。デジタイゼーションとデジタライゼーションはどちらも業務工程をデジタルの力によって効率化していくものです。デジタイゼーションはデジタルツールを導入することで特定業務のデジタル化やアナログ情報をデジタルにしてデータを蓄積できる環境を整えることを言います。
たとえば、営業職が商品説明をするときに、従来は紙の資料やパンフレットを使っていたものが、タブレットで説明をしたり契約時のサインを電子署名にしたりすることなどが挙げられます。また、病院で手書きだったカルテが電子カルテになるのもデジタイゼーションの一例です。
デジタイゼーションの次のステップであるデジタライゼーションは業務フロー(プロセス全体)をデジタル化していくことです。病院の例で言えば特定の病院内でのみ閲覧できる電子カルテを、1つの病院だけでなくすべての病院で閲覧できるような状態です。
デジタイゼーション、デジタライゼーションの先にあるデジタルトランスフォーメーションは、特定の業務や業務フローをデジタル化することではありません。デジタルを使って企業や顧客、ひいては社会全体の生活スタイルを変革しようとするもので、最終的には製品やサービスもデジタル化することを言います。デジタルトランスフォーメーションとデジタイゼーションやデジタライゼーションは混同しやすいものですが、同列のものではなく、段階を経た先のものだと考えてください。
現在の課題はデジタライゼーションにある
実は現在語られているデジタルトランスフォーメーションは、そのほとんどが第二段階のデジタライゼーション、つまりプロセスのデジタル化です。業務全体をデジタル化できるかどうかが日本においては課題であると言われています。それぞれの病院では電子カルテが導入されていても、すべての病院でそれが共有できる状態には現段階ではありません。
営業活動を見てみても、実際に訪問せずにオンラインや電話で商談を行うのは失礼にあたるとする考えが日本にはあります。そのようなところもデジタルトランスフォーメーション、デジタライゼーションが発展しづらい理由となっているのかもしれません。
デジタライゼーション・デジタルトランスフォーメーションの成功例
現代において、デジタルトランスフォーメーションにかなり近いとされる成果を上げた企業があります。 概念としてデジタルトランスフォーメーションを理解できても、「自社におけるデジタルトランスフォーメーションとはどのような状況にあることか」は、即座に答えが浮かぶものではありません。先を行く企業の事例を知ることでデジタルトランスフォーメーション推進の参考にしていきましょう。
大塚製薬
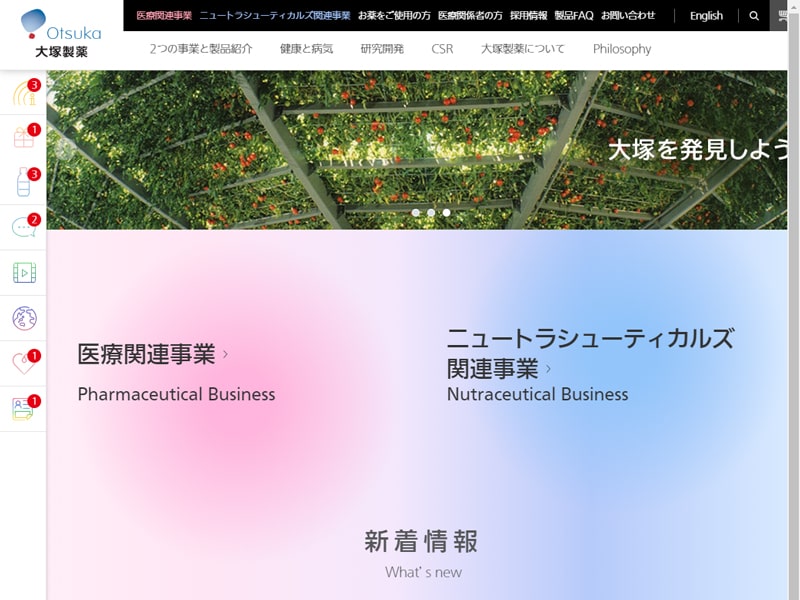
出典:https://www.otsuka.co.jp/
大塚製薬は医療IoTを活用した服薬支援システムを開発しています。薬の飲み忘れを防ぐために、薬剤が入った容器が決められた時間になると容器のLEDが自動で点灯し、服薬時間であることをお知らせしてくれます。薬を飲んだことも容器が検知し、そのデータをスマホやタブレットに送信できるので、本人だけでなく家族にも服薬状況の共有が可能です。
医療・介護の効率化や病気の再発・悪化の防止、ひいては社会保障費の削減が期待できる点など社会的意義の大きさにも注目が集まっています。自分が飲んでいる薬を記載するおくすり手帳は、まだまだアナログの世界です。災害時などには、おくすり手帳の有無で適切な医療処置ができるかどうかが変わってくることもあります。大塚製薬の服薬支援システムが、将来的には災害の現場を救うことになるかもしれませんね。
大塚デジタルヘルス

出典:https://www.mentat.jp/jp/
大塚デジタルヘルスは精神科医療に対する電子カルテデータ分析をサービスとして成立させた、大塚製薬と日本アイ・ビー・エムが設立した合弁会社です。従来、精神科医療では個々の病状や病歴を数値として表すことが難しく、そのためカルテには医療従事者によって自由記述の欄にデータが蓄積されてきました。しかし自由記述であるがゆえに、たとえば「この薬を使用している患者で、似たような症例の人を見つけたい」と考えてもデータベース上での検索は困難で、カルテ管理に対し大きな課題がありました。
そこでアイ・ビー・エムが開発した人工知能の「Watoson」とクラウドサービスを組み合わせることで、患者情報を一覧で閲覧しやすくするほか、断片的だった処方履歴の変化を一覧で表示できるようになりました。病院内では、患者や家族へ類似症例や統計データを元にした説明が行えるほか、データ分析や症例レポートの作成をサポートが可能になりました。またクラウドの共有により、400万人弱とも言われる症例を利用した治療への反映が期待されています。
三菱電機

出典:https://www.mitsubishielectric.co.jp/
三菱電機が考案したリモートサービス「iQ Care Remote4U」は、放電加工機やレーザ加工機にIoTを活用したものです。従来は工場でトラブルやエラーがあった際は、職員が現場に急行し、実際現場の状況が分かるまでにタイムラグがありました。そのため、トラブルやエラーの原因解明や顧客への対応が遅れるといった課題がありました。
しかし製品が稼働している工場・データセンター・三菱電機サービスセンターがIoTでつながりあうサービスを実施することで、どこで何が原因でトラブルが発生したのか把握しやすくなり、製品の状態を遠隔でチェックすることができるようになってきています。アラームの内容もサービスセンターから把握できるので、対応もスムーズに行えます。
メルカリ

出典:https://www.mercari.com/jp/
フリマアプリで知られるメルカリ。メルカリの登場以前は、それまでは中古品の売買はPCで行うインターネットオークションが主流でした。メルカリはユーザーの利便性を重視しPCがなくてもスマホアプリで完結するという大きな進化を遂げています。従来のインターネットオークションでは個人間で売買を行う場合でも実名でやりとりを行うことが前提となっていました。しかしメルカリでは匿名配送といって、購入側の実名が分からなくても配送できるサービスも実現しています。
個人情報が扱いが気になる現代では、匿名配送は非常に大きなメリットだと言えるでしょう。面識のない相手との実名でのやりとりに抵抗がある人は少なくありません。売買がスマホで完結するという主軸の部分だけでなく、配送という点に着目することは、利便性以上にユーザーの信頼を得ることにもつながっています。
グンゼ

出典:https://www.gunze.co.jp/
アパレルメーカーのグンゼは、衣類のIoT化に着手しています。NECの薄型デバイスを活用し、生体情報を取得できる繊維を開発しています。特殊繊維で作られた下着を着ることで、着用者の動きや姿勢の癖、消費カロリー、活動量などを可視化できるものになっています。
グンゼはアパレル事業のほかに、約20店舗のスポーツクラブを全国に展開しています。自社のスポーツクラブで、すでに実証実験がおこなわれています。将来的にはこの技術を使って、高齢者のサポートや労働現場で働く従業員の体調管理など、新たなビジネスにつなげていく構想が立てられています。
小松製作所

出典:https://home.komatsu/jp/
建設機械・鉱山機械メーカーである小松製作所は、2015年から「スマートコンストラクション事業」をスタートし、デジタルトランスフォーメーションを推進しています。小松製作所では、デジタルトランスフォーメーションを「お客様の課題解決を実現するための手段」と位置づけ、慢性的な人手不足と作業中の怪我のリスクに悩まされる建設業界を、ICTの力で改善しようとしています。
ICTとは「Information and Communication Technology(情報通信技術)」の略で、通信技術(=IT)を活用したコミュニケーションを指します。情報処理だけではなく、インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどの総称です。具体的には従来、人力に依存していた測量や調査、設計、施工計画といった業務を、ドローンやデジカメ、クラウドを使ったシステムで実行し、自動化することで、生産性と安全性の向上を実現するというものです。
ICTを搭載した機械はレンタルと販売の両方で提供。ドローンの活用により、人手では何日もかかるような広大な土地の測量でも1日で、しかも高精度に行えるなど、業務効率化・生産性向上が可能となります。2020年3月には、同事業を海外展開することを発表しています。米国と欧州4ヵ国(英国、ドイツ、フランス、デンマーク)においてすでに市場導入を開始しています。
家庭教師のトライ

出典:https://www.trygroup.co.jp/
家庭教師のトライは個別指導スタイルが特徴の家庭教師事業を30年以上展開しています。従来の家庭教師は、生徒と1対1で個別に指導を行うというスタイルです。しかし生徒の学習スピードは個々に違いますので画一的なカリキュラムでは不十分となります。さらに生活スタイルの多様化により実際に自宅に訪問して授業を行うだけでは指導しきれない課題がありました。
そこで家庭教師のトライでは、映像学習サービスの「Try IT」というサービスを実施しました。これは、トライ会員であるかどうかに関わらず単元ごとの映像授業を無料で視聴できるというもの。元来学習塾や家庭教師というのは、管轄地域にいなければ授業が受けられませんでしたが地域や経済の格差を超えて、自由に勉強できる学びの場を提供するという点で、大きな社会貢献として注目されています。
学習塾には大きく分けて個別指導と集団指導の2つがあります。学習塾の利用者のほとんどは夏休みや冬休みといった長期休暇に実施されている夏期講習・冬期講習に参加します。しかし講習期間中は授業の回数が多くなりますので、当然費用負担も大きくなります。無料で学習できるというサービスの実施は、今後の塾業界のあり方を大きく変えていくかもしれません。
ウェザーニューズ

出典:https://jp.weathernews.com/
ウェザーニューズ社は世界最大の民間気象情報会社であり、気象庁が独占していた気象情報を独自に提供する仕組みを開発したことで知られています。現在、ウェザーニューズの予報を使用している放送局は、全体数の70パーセントを超えています。天気予報をするための情報の入手は、デジタル化以前はニュースや新聞などに限られており、リアルタイムで天気予報を行うのは困難でした。
ウェザーニューズでは独自に船舶運航企業に気象情報の提供を開始するシステムを運用し、気象庁が独占していた情報を企業として提供できるようにしました。その結果、海や空の航路の安全性を確保につながるとされ、それまで「買う人はいない」と言われていた天気予報をビジネスとして成立させました。今では、170億円の売上がある上場企業にまで成長しています。
ベネッセコーポレーション

出典:https://www.benesse.co.jp/
こどもちゃれんじや進研ゼミといった通信教育システムで知られるベネッセコーポレーション。赤ペン先生と呼ばれる担当制で添削を行うシステムを採用していますが、紙媒体でのやりとりとなるので市場のニーズに合致していないという課題を抱えていました。
この課題へのアプローチとして、ベネッセコーポレーションでは小学生向けの講座に「チャレンジタッチ」というタブレットを活用した学習スタイルを導入し、今の時代にあった新しい通信教育を実現しています。ゲーム感覚で勉強ができるという子ども目線のメリットだけでなく、親からはスマホで学習状況の確認ができる機能が備わっていますので、安心できるという特徴もあります。子どものうちに勉強を楽しめるかどうかは、将来にも大きく関わってきます。スマホで検索すればすぐ答えが出る世の中であるからこそ、自ら学ぶことの重要性は今度ますます大きくなってくるはずです。
学研ロジスティクス

出典:https://www.glg.co.jp/
物流事業を広く手掛ける株式会社学研ロジスティクスは、ダイレクトマーケティングの支援など、システム提供を通して企業をサポートする会社です。しかし、申込書や引き落とし用紙が紙媒体であったことから、繁忙期には膨大な入力作業が生まれ、入力専門の人材を雇用しなくてはならないほどでした。
この課題への解決方法として、学研ロジスティクスでは紙媒体をなくすことではなく、手書きの文字を高い精度で読み取ってくれるサービス「DX Suite」と、RPAと呼ばれるあらかじめプログラムしておいた作業を自動で行ってくれるツールを連携させ、申込書や引き落とし用紙を自動的に読み取るシステムを作り上げました。スキャンしたデータを読み込んだ後、確認修正にも利用できるため、大幅な業務時間の改善を実現しています。
三井住友銀行

出典:https://www.smbc.co.jp/
三大メガバンクの一つである三井住友銀行では、顧客の声を「見える化」するデジタルトランスフォーメーションに取り組んでいます。企業において重要な「お客様の声」。それらをまとめる作業は非常に重要なものではありますが、年間に35,000件もの声が寄せられる状況にある三井住友銀行では、お客様の声をまとめたり仕分けたりするだけでも多くの時間と人件費が必要となることが課題でした。
そこで三井住友銀行では、寄せられた意見や要望をNECの「テキスト含意認識技術」を利用し、書かれている内容別にグループ分けを行えるシステムが開発されました。人力で行うよりも高度な分析を実践できるだけでなく、業務の効率化、それまで得ることができなかった新たな意見の抽出にもつながっています。
ソフトバンク

出典:https://www.softbank.jp/
携帯電話大手キャリアの1つであるソフトバンク株式会社では、コールセンターの業務効率化をデジタルトランスフォーメーションによって実現しています。 ソフトバンクには、毎月約6000件近くの「携帯電話の落とし物通知依頼書」が届いており、それをデータ化するための入力に多くの人員を割いていました。人員はコールセンターに在籍しているオペレーターから割いていたのでコールセンター業務で支障が発生することも少なくありませんでした。
この課題を解決するために、ソフトバンクではすでに導入しているシステムと連携可能な、手書きの文字を読み取ってデータ化するサービスを新たに取り入れ、データ化したCSVを自社開発システムに入れ、RPAで専用のシステムを使うことで入力作業の自動化に成功しています。
携帯電話には個人情報がつまっていますので限られたネットワーク環境でしか業務が行えないという性質がありますが、それを見事に克服した例と言えます。入力作業の自動化に成功したことで、これまで10人のオペレーターで行っていた携帯電話の落とし物通知依頼書の入力作業が、1人で完結できるようになり、全体で考えると月に200時間もの業務効率化に成功しています。
三越伊勢丹ホールディングス

出典:https://www.imhds.co.jp/ja/index1.html
三越伊勢丹ホールディングスは「ITと店舗、人の力を生かした新時代の百貨店(プラットフォーマー)」をスローガンにデジタル戦略に注力しています。百貨店の商品を通販で買うというイメージはあまりない方が多いのではないでしょうか。実は百貨店では従来「商品のデータベース管理」が弱点とされていました。それもそのはず、百貨店とは1つの大きな建物のなかに数えきれないほどのテナントが入っているため、全体の商品を一括でデータベース管理することは簡単ではないのです。
その弱点を補うために、三越伊勢丹ホールディングスでは、商品撮影用のスタジオを新設し、基幹店が扱う全商品をECサイトでも地域店でも購入できるシステムを確立しました。チャットを活用したパーソナルスタイリングサービスの導入や、オンライン・オフラインの双方で上質な顧客体験を提供することで新たな顧客層の獲得も見込まれています。
Uber

出典:https://www.uber.com/jp/ja/
Uberはデジタルトランスフォーメーションを象徴するサービスと言えます。Uberと言えばUber Eatsが日本では有名ですが、タクシーの配車サービスも主力の事業です。ユーザーはUberアプリだけでタクシーの配車から目的地の指定、決済までを行うことができます。もともとはアメリカ発祥ですが、2018年に日本への本格参入がスタートしました。タクシー会社とUberが協業し、サービスの提供をおこなっています。そして民間だけでなく、自治体での活用事例も出てきています。
そのうちのひとつが、京都府丹後町で行われている「ささえ合い交通」です。本来、タクシー業を営むには2種免許が必要なのですが、過疎地域においては例外が認められています。バスやタクシーが提供困難な場合、「自家用有償旅客運送制度」を活用することで自家用車にて乗客の輸送が可能になります。ささえ合い交通では、地域住民がドライバーとなってタクシーの役割を担っています。乗客はUberアプリを使って配車から決済までが一括で可能です。料金もタクシーの約半額となっているので観光だけでなく、通院やお買い物といった市民の足としても有効活用されています。
MicroSoft
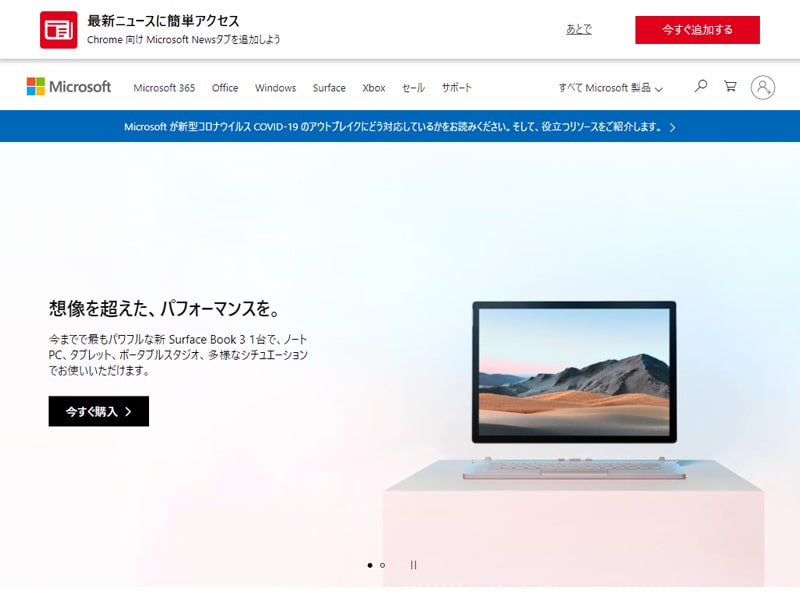
出典:https://www.microsoft.com/ja-jp
OSの中でも特に利用者の多いWindowsや、Word・Excel・PowerPointなどのOfficeソフトで知られるMicroSoftは、Officeソフトのクラウドネットワークサービスを始めました。それまでOfficeソフトというと家電量販店などでパッケージを購入して自身でPCにインストールするという買い切り型のものでしたが、MicroSoftではサブスクリプションといって月額課金型のサービスを主流とするように移行しました。
買い切り型では新しいバージョンになる度に買い直す必要がありますが、クラウドネットワークサービスとすることで常に最新のバージョンを定額で使えるというメリットがあります。この結果、費用の問題で買い切りだと使用を断念していたユーザーにもアプローチできるようになり、新たに顧客層を広げることに成功しています。
Amazon

出典:https://www.amazon.co.jp/
Amazonが創業した当時はWindows95の発売前で、まだ「インターネットを経由して本を販売する」ということ自体が新たなビジネスモデルでした。実際に本屋がたくさんある中で、インターネット上の本屋を選ぶ理由がなかったのです。そこでAmazonはユーザーファーストを徹底し、インターネット書店ならではの機能としてカスタマレビューやおすすめ機能を実装していきました。またワンクリックですぐに購入できるようにし、面倒な情報入力の手間をなくすことにも成功しています。
結果としてAmazonは「最高の顧客体験」をテーマに多くのサービスを実践し、爆発的にシェアを拡大していきました。この成功は、世界で最もデジタルトランスフォーメーションの実現に近いと言われています。
ベストバイ

出典:http://www.bestbuy.co.jp/
ベストバイはアメリカに本社を置く世界最大の家電量販店です。実店舗とWebサービスを組み合わせたことで収益増加を達成しました。家電量販店では、実店舗で買い物をするのが通常です。そのためAmazonなど通販サイトが広く利用されるようになるにつれ、純利益が減少し、2012年には90%ダウンというとても深刻な状況に陥っていました。
そのような状況のなか、ベストバイではネットで注文した商品を店頭でも受け取れるようにしたり、顧客がネットで他店でより安く売られているのを見つけた際には安いものと同じ価格で購入できるようにしたりするなど、Webサービスと実店舗をリンクさせるようにしました。Webサイトも使い勝手がよいように店舗在庫の即時反映などを行うといった改善も行うことで収益を大幅に回復させることに成功しています。
デジタルトランスフォーメーション推進への課題
今回はデジタルトランスフォーメーションに成功した例を紹介しました。しかし各企業はデジタルトランスフォーメーションの重要性を認識し、ある程度の行動を起こしているものの、実際のビジネス変革には至っていないところがほとんどです。 デジタルトランスフォーメーションを本格的に展開していく上ではさまざまな課題があり、それらをクリアできないと「2025年の崖」と呼ばれる取り返しのつきづらい状況に陥ると言われています。
既存のITシステムのブラックボックス化
企業では、業務を行うにあたってすでに何らかのITシステムが導入されています。業種によっては数十年単位でシステムの変更が行われていないというケースも珍しくありません。企業は自社が運用しやすいように既存のシステムをカスタムし続けるのが通常です。そのためシステムが老朽化するだけでなく複雑化することで、どんなものなのか実態が見えないブラックボックス化している状態にあります。
システムのブラックボックス化がすすむことでデータを活用しきれないだけでなく、新たな技術を導入しても効果が出にくい状況にどんどんとはまってしまいます。さらには、新たなシステムを1から導入するためには、仕事のやり方そのものが大きく変更する必要があるため、現場からの抵抗も大きいことも、ブラックボックス化がすすむ要因となっています。
もちろんシステムの刷新には大きな費用と時間がかかります。しかし、これらの問題を放置しておくと、「デジタル市場の拡大に伴って大きくなるデータ量」・「システムを現場で運用している担当の定年退職による世代交代」・「サイバーセキュリティや事故・災害などによるデータの紛失リスクの高まり」といった状況に陥ると考えられています。
これら3つの要素に対応しきれなくなるのが2025年と言われており、2025年までにデジタルトランスフォーメーションが起こせなければ、国内外を含めて競争に勝ち残れない存在となると予想されています。
2025年への期限は迫っており、現在は「システム刷新集中期間(DXファースト期間)」として既存システムの刷新が推奨されている時期にあたります。業務プロセス全体のデジタル化を行うのは期間がかかることなので、段階的な変更も必要となるでしょう。 しかし企業が生き残っていくためにはデジタルトランスフォーメーションは必須です。自分が所属している企業において、ブラックボックス化しているものはないか周りを見てみることから始めてみてはいかがでしょうか。







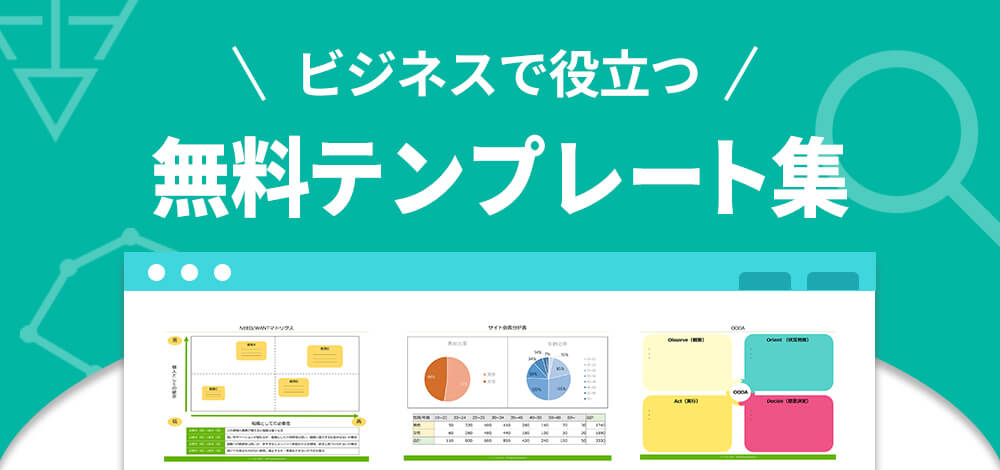
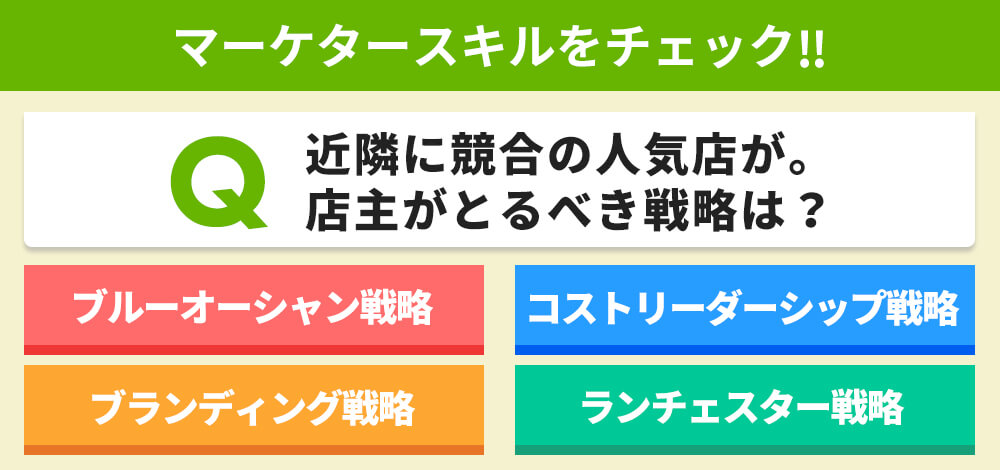
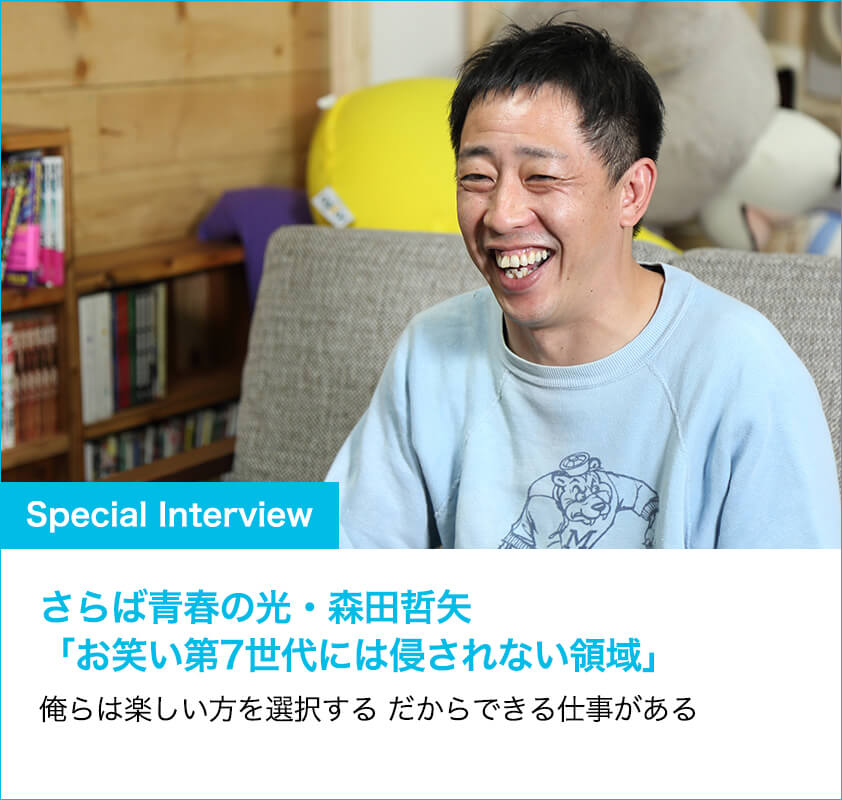


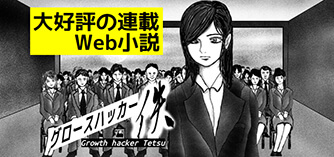


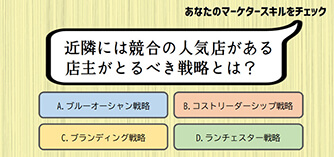
.jpg)

