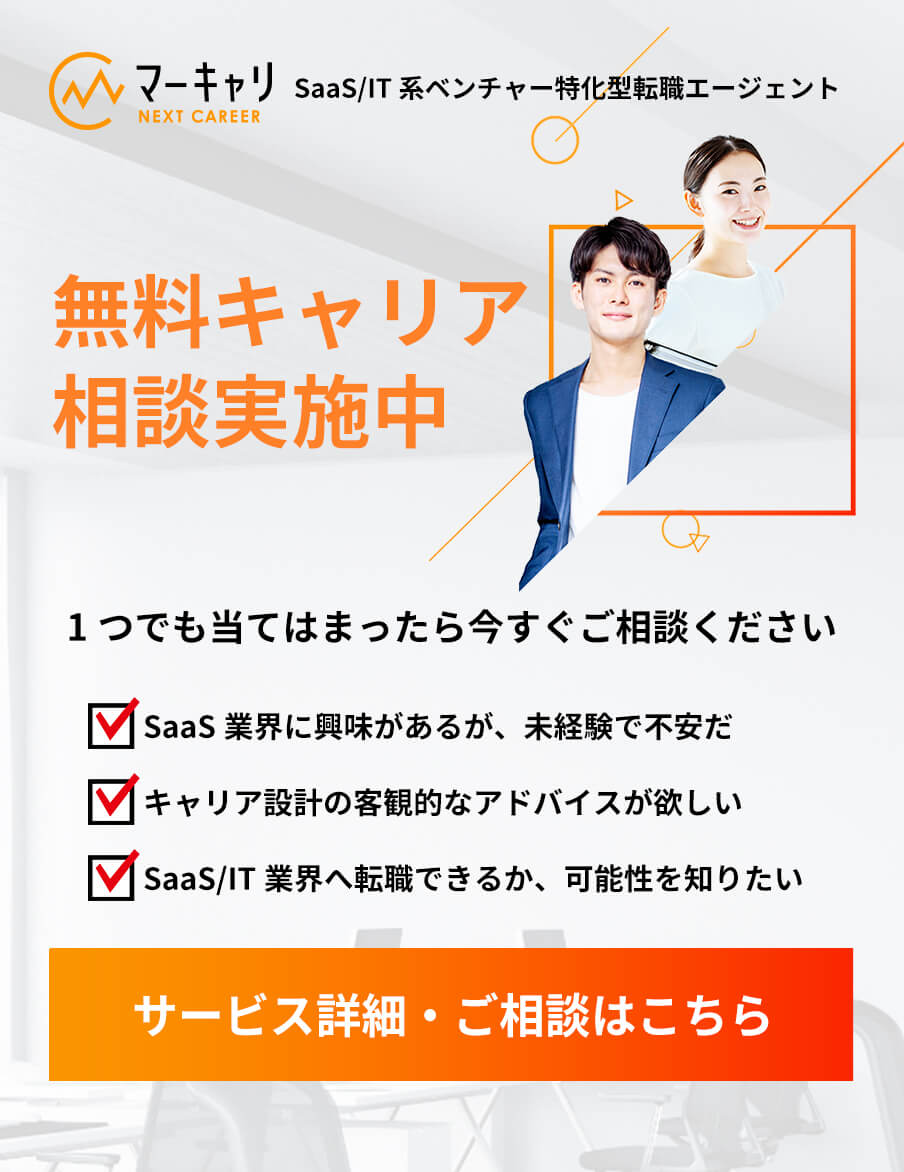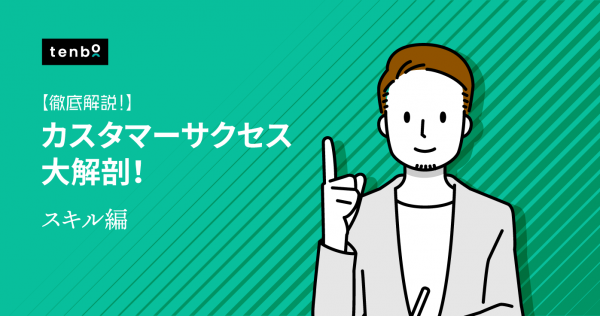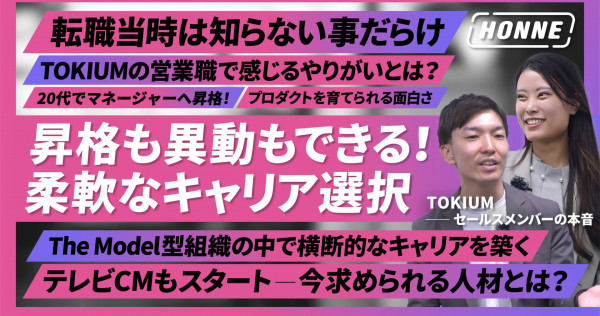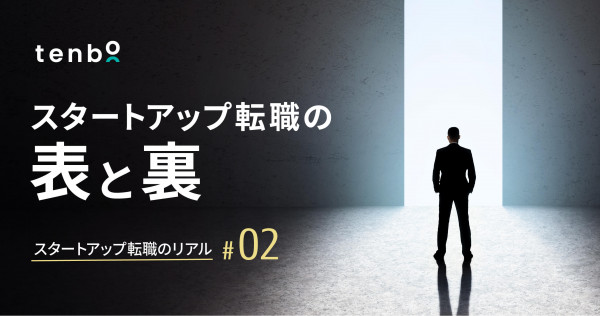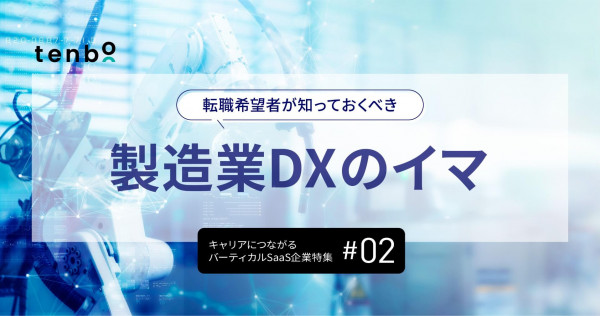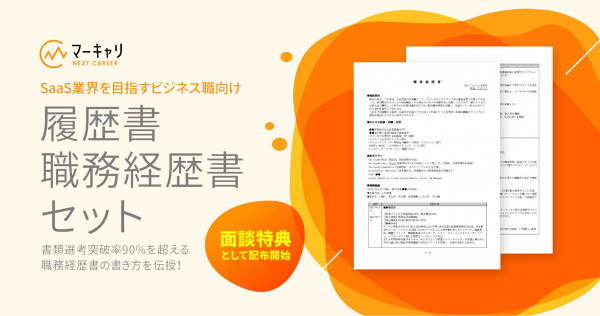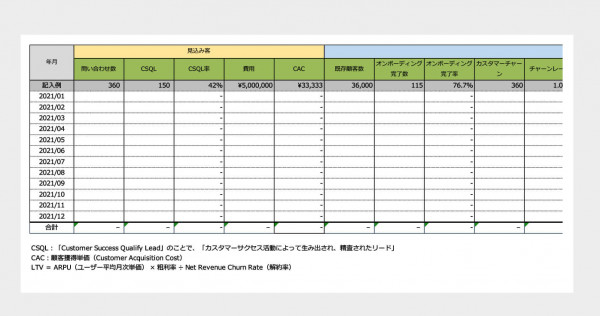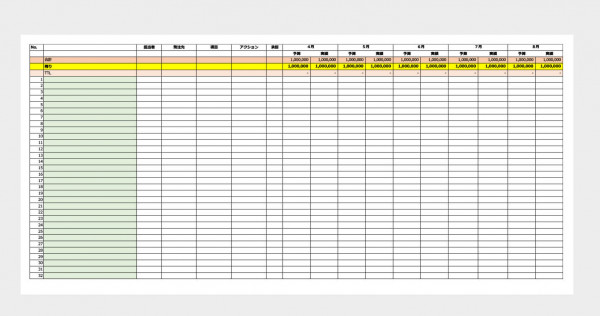- 目次
この記事では「SaaS」について基礎から詳しく解説しています。SaaSの特徴や導入メリットだけでなく、代表的なSaaS企業についても触れていきます。ぜひお役立てください。
1. SaaSとは
SaaSは「Software as a Service」の頭文字をとったもので、読み方は「サース」や「サーズ」です。直訳すれば「サービスとしてのソフトウェア」となり、クラウド上で提供されるソフトウェアのことを指します。
クラウドとは、「クラウドコンピューティング」のことで、従来のようにPC内にインストールされているアプリやデータではなく、インターネット経由でアプリケーションを使うことを言います。
多くのサービスでは、自分のPCにCD-ROMなどに入ったソフトをインストールする必要がないので、PC自体の容量が圧迫されません。アプリケーションは時代とともに複雑化、高性能化しているため、できることが増えればその分、PCの容量が必要になるのが通常です。しかし、SaaSであれば一定のPCの処理能力さえあれば、問題なく動作します。PC内にソフトをインストールするわけではないので、アカウントがあれば、PCでなくてもタブレットやスマートフォンからもログインして動かすことができます。
SaaSを商品として提供する企業をSaaS企業と呼びます。SaaSには既に「サービス」の意味を含んでいますが、SaaS企業が提供するサービスをSaaSサービスと呼ぶことが多いです。

1-1. SaaSの特徴
SaaSの最大の特徴は、アプリケーションをインターネット上で使用する点にあります。このことによりさまざまなメリットが得られる一方で、オフラインではアプリケーションを動作させることはもちろん、情報の確認すらできないことには一定の注意が必要と言えるでしょう。
2. SaaS・PaaS・IaaSの違い
ある程度自社でカスタマイズをしたい場合には、SaaSより自由度の高い「PaaS」や「IaaS」といったものがあります。「PaaS」は「Platform as a Service」の略称で、開発に必要な言語や管理システム、OSなどのプラットフォームサービスのことです。複雑で面倒な開発環境を整備する手間がなくなるというメリットがあり、システム開発に注力したい場合に適しています。
また「IaaS」は「Infrastructure as a Service」の略称で、システムの稼働に必要な仮想サーバやハードディスク、ファイアウォールなどのインフラを、インターネット上のサービスとして提供する形態です。サーバやセキュリティ全般を見直したい場合に適しています。
SaaSは企業から提供されるサービスをそのまま使っても不自由や不都合がない場合に適しているといえます。
3. SaaS導入のメリット
ここでいうSaaS導入とは、自社がSaaSサービスの展開を始めるという意味ではなく、他社製品としてのSaaSを自社が導入することで得られるメリットのことです。
SaaSの導入には大きく分けて5つのメリットがあります。
3-1. SaaS導入のメリット(1)インターネット環境があればどこからでもアクセスできる
PC自体にソフトをインストールするものであれば、当然そのPCからでしかソフトの起動ができません。しかしSaaSの場合、ソフトウェアはアカウントごとに提供されているので、複数のPCから、さらにはスマートフォンやタブレットからもアクセスできます。テレワークを行う場合にも、既存のアカウントがあれば、そのまま各デバイスから利用できます。
3-2. SaaS導入のメリット(2)複数の担当者がデータを共有し同時に編集・管理できる
SaaSでは、データの保存もクラウド上で行われています。そのため複数の人間で同時にデータファイルの共有ができますし、データの管理や編集も可能です。
このことにより、既存業務の属人化を防ぐ効果も期待できます。担当者のPC内にしかデータがないから分からない、担当者が急遽休みになったから代わりに別の人がフォローしようとしても、データが共有できなくて何もできない、といったことが防げます。
3-3. SaaS導入のメリット(3)導入コストが安い
SaaSでは、既にクラウド上にソフトウェアがあり、それをユーザーが利用します。そのため自社で新たにソフトウェアを開発する必要がありません。また、これにより、ソフトウェアを自社用に開発する費用や時間が削減できます。結果としては自社で一から開発をするよりは、安価になり、社内のユーザー数に合わせてアカウントを増減させれば、無駄なコストがかからなくなります。パッケージ製品の場合は、前任者が使っていたPCを引き継がなければならないのが一般的でしたが、SaaSならそのような手間もなくなります。
3-4. SaaS導入のメリット(4)安いランニングコストで、常に最新のソフトが使える
パッケージ製品の場合や、自社でソフトウェアを開発する場合には、セキュリティ対策や最新バージョンへのアップデートはユーザー自身が行う必要があります。しかしSaaSではサービスの提供側がバージョンアップを行いますので、ユーザーは常に最新版の利用が可能です。
3-5. SaaS導入のメリット(5)気軽に導入できる
導入コストの安さとランニングコストの安さにより、SaaSは従来のソフトウェアに比べて気軽に導入可能なこともメリットの1つです。
常にアップデートが行われるSaaSは、買い切り型ではなく、月額課金のサブスクリプション型の収益体制となっていることが多いです。
例えばアドビ社の「Illustrator」は、買い切り時代は10万円近くもしたソフトで、なかなか初心者には手が出しづらいものでした。しかしサブスクリプションに移行したことで月額2,000円程度での利用が可能になっています。
これにより、新規ユーザーがソフトを使用することの敷居が低くなりました。アドビ社が2011年にサブスクリプションへ移行した際は、一時的に売上額も減少しましたが、2016年には新規ユーザーの獲得に成功し、過去最高の収益を達成しています。
単純に消費を拡大していくことが困難な現代において、従来のビジネスモデルが限界を迎えつつあることに危機感を感じた企業が、いち早くサブスクリプションビジネスへと移行しています。
SaaSのようなサブスクリプション型ビジネスは、ユーザーにとっては導入への敷居が低くなり、企業にとっては安定して継続収入を得られることと新規ユーザーを獲得しやすくなるといったメリットがあります。
4. SaaS導入によるデメリット
メリットの多いSaaSですが、デメリットがないわけではもちろんありません。インターネット上でソフトウェアを起動するSaaSでできることは、当然ソフトウェアの範囲に限定されています。つまりは自社が使いやすいように独自にカスタマイズを加えることや新たな機能の追加は基本的にできません。
自社の業務にぴったりのSaaSがあれば問題はありませんが、もし見つからない場合は、提供されているサービスに合わせて業務の仕方を変更したり、別のアプリケーションやソフトウェアで補ったりする必要があります
自社の業務効率化や、収益最大化のために導入するサービスが、かえって社員の業務を増やしてしまうのは避けたいところです。そのため、数えきれないほどのSaaSがある中で、いかに自社にとって使い勝手のよいSaaSを選定するかが、非常に重要になります。
ある程度自社でカスタマイズをしたい場合には、SaaSではなく自由度の高い「PaaS」や「IaaS」を導入することも選択肢に入れるとよいでしょう。
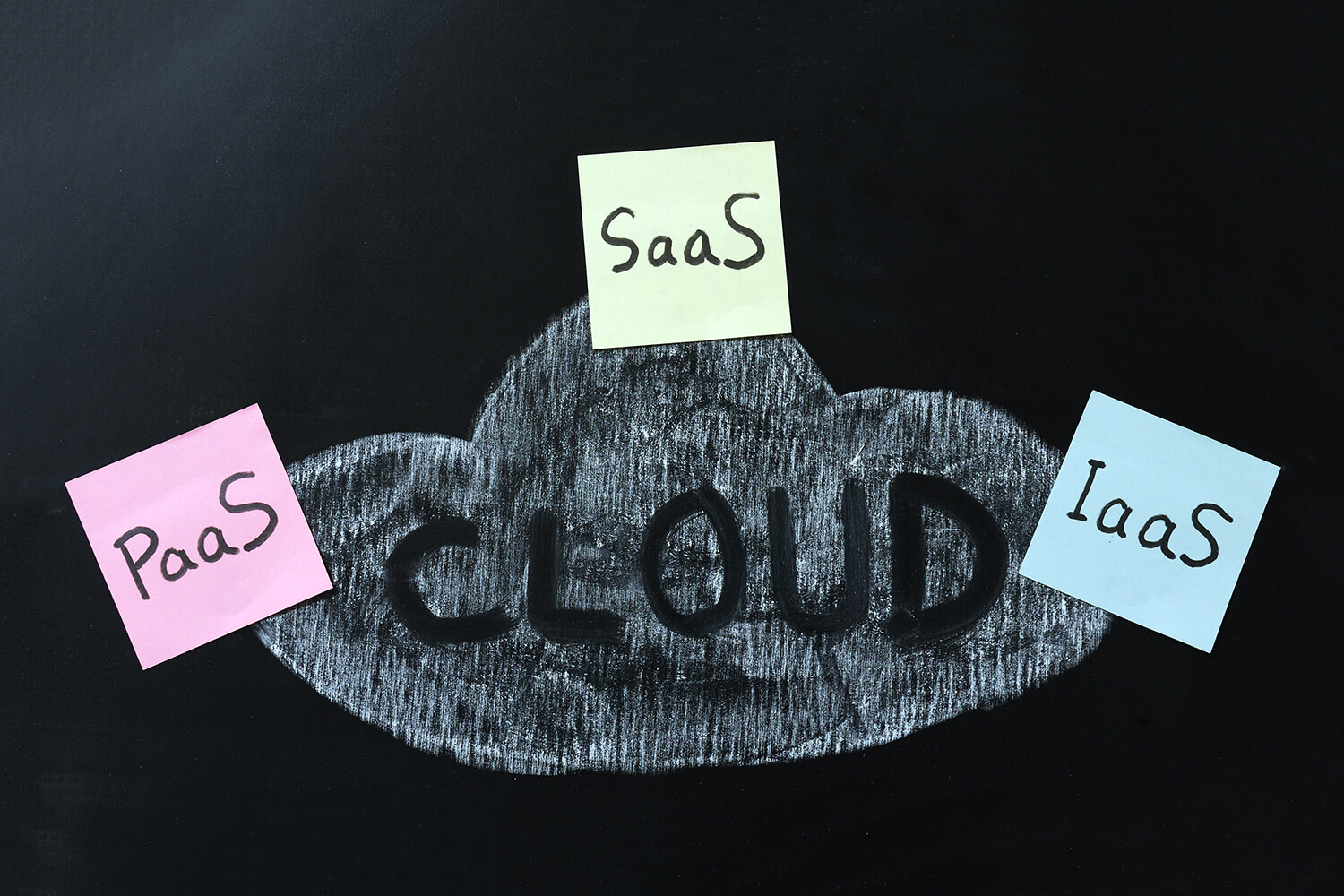
5-1. PaaSの特徴とメリット・デメリット・代表例
PaaSでは、アプリケーション開発・実行に必要なOSやデータベースをインターネット上で利用可能です。開発環境が整っているところからスタートできるので、自社で一から準備するのと比べると初期費用や運用コストが削減できますし、インフラについての設計や管理が不要なので効率的に開発が進められます。
PaaSは使用したものに対してだけ料金が発生する従量課金制であることが多く、企業は必要な機能のみを選んで使用できます。
PaaSの代表例としてはAmazonが提供する「Amazon Web Services(AWS)」、Googleが提供する「Google App Engine」、Microsoftが提供する「Microsoft Azure」が挙げられます。
5-2. IaaSの特徴とメリット・デメリット・代表例
IaaSはインターネット上で提供されるネットワークインフラです。IaaSを使えば自社でサーバやストレージなどのハードウェアを用意しなくても、ネットワークを構築できるようになります。自社専用のネットワークを構築するためのものなので自由度は高いですが、その分専門的な知識や技術が必要になります。
IaaSの代表例としてはPaaSとしての性質も併せ持つ「Amazon Web Services(AWS)」に加え、Googleが提供する「Google Cloud Platform」、日本産のIaaSサービスである「さくらクラウド」などが挙げられます。
6. ホリゾンタルSaaSとバーティカルSaaS

SaaSは「ホリゾンタルSaaS(Horizontal SaaS)」と「バーティカルSaaS(Vertical SaaS)」の2つに分けられます。
ホリゾンタルとは「水平な」という意味で、ホリゾンタルSaaSは業種や業態に関係なく、どの企業でも行うような業務に特化したSaaSです。例えば会計業務や人事関連業務などを管理するSaaSはホリゾンタルSaaSです。
バーティカルSaaSのバーティカルとは「垂直な」という意味があります。バーティカルSaaSは特定の業種向けにカスタマイズされたSaaSのことをいいます。
バーティカルSaaSは、小売や製造業など、特定の業種向けに特化しているため、どこの企業でも有用なわけではありません。しかし、特定業種向けにカスタマイズされている分、導入する企業側でカスタマイズが不要になりやすいというメリットがあります。
現在、日本で多いのはホリゾンタルSaaSです。しかし、ホリゾンタルSaaSは「どの企業でも使える」ことを念頭において開発されるため、あらゆる業種の企業がターゲットとなり、多くのSaaS企業が参入しています。多くの商品が世に出ているため、どうしても他社商品との差別化が図りづらいという特徴もあります。ホリゾンタルSaaSが一種の飽和状態になれば、差別化を図る意味でバーティカルSaaSが増えてくることが予想されます。
7. SaaSの料金体型
クラウド上で提供されるSaaSは、常に最新版にアップデートされるということもあり、ほとんどが買い切り型ではなく、サブスクリプション型で提供されています。基本的にはいくつかのコースが用意してあり、自社にあったものを選択し、コースの範囲内で可能なことを実施していく流れになります。
買い切り型に比べて導入コストが安く済むというメリットを活かして、複数サービスを試してみてその中で自社の業務の進め方にマッチしたものを選ぶという方法もあります。
8. SaaSの代表例

SaaSはクラウドで提供されるソフトウェアで、サービスを提供する側(ベンダー)でソフトウェアを稼働させて、ユーザーはネットワーク経由でソフトウェアを活用するものになります。身近なSaaSの例で言えばGoogleが提供するGmailがあります。
スマートフォン以前の携帯電話に届いていたe-mailは、携帯電話の中に保存されていました。そのため圏外であっても受信済・送信済のメールは確認できました。しかしGmailの場合は、インターネット環境がなければページに行くこともできません。これはGmailというソフトウェアがSaaSだからこその現象です。基本的にPCやスマホは常にインターネットと接続されているので意識することはないでしょうが、Gmailがクラウド上にあるものだということの表れです。
SaaSの代表例であるGmailは元々パッケージ製品として販売されていたものではありませんが、技術の進歩により、パッケージ製品がSaaS化したものがあります。有名なもので言えばWordやExcelといったOfficeソフトと、IllustratorやPhotoshopといったデザインソフトです。WordやPowerPoint、Excelは買い切りのパッケージ版もありますが、PhotoshopやIllustratorは現在では完全にSaaSに移行し、月額課金型・従量課金型のサブスクリプションビジネスへと転換しています。
SaaS企業が増えている理由は、買い切り型のビジネスよりも継続課金型のビジネスにメリットを感じている企業と、実際にビジネスモデルを転換している企業が多いからです。
8. コミュニケーションツールのSaaSサービス例
ここからは具体的なSaaSサービスについて紹介していきます。まずは社内やクライアントとのコミュニケーションに有用なサービスを紹介します。
8-1. Slack

出典: https://slack.com/intl/ja-jp/
Slackは、2013年8月にアメリカでリリースされたコミュニケーションツールで、日本でも利用者が急増しています。チャット機能、ファイル機能、検索機能、ビデオ通話機能があります。1対1での通話だけではなく、チャンネル内のメンバーとも通話が可能で、最大15名まで同時に通話ができます。
検索機能が優秀で、発言者を絞った検索や、期間を絞った検索も可能です。
デスクトップ版の有料プランの場合だと、相手と画面を共有する、共有している画面に書き込みをするといった機能も使えます。
GoogleカレンダーやGoogleドライブなど、多くの外部ツールと連携可能な点も特徴的です。
8-2. Zoom

出典: https://explore.zoom.us/ja/products/meetings/
現在急速に認知度を高めているWeb会議システムです。参加するだけならアカウント登録は必要ありません。PCはWindowsかMac、スマートフォンならiOSとAndroidをサポートしているため、多くの方が利用できます。無料プランでも100人までの同時接続が可能です。また、会議の映像や音声を記録でき、部屋の中を見せたくない人に向けてバーチャル背景を映すといった機能も備わっています。これまでは1対1の個人間ミーティングであれば、無料プランでも「時間無制限」でしたが、2022年5月より仕様が変わり、1対1の場合でも最大40分までに変更となりました。
8-3. Google Workspace

出典: https://workspace.google.com/intl/ja/
Google Workspace は、Google が提供する組織向けのオンラインアプリケーショングループのことです。GmailやGoogle カレンダー、Googleドライブなどを中心として、グループ内のコミュニケーションや、ファイル作成といったさまざまなアプリケーションを目的に合わせて利用できます。
主に4つの料金プランがあり、最もシンプルなものでも、100人まで参加可能なビデオ会議ができるなど、優れた機能を持っています。
8-4. Microsoft Teams

出典: https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software
Microsoft Teamsの最大の特徴は、各種Office 365ツールと連携できる点です。メンバーとチャットする機能、資料を共有する機能、通話やビデオ会議を開催する機能もあります。モバイルアプリも提供されているためTeamsを起動すると、場所や時間を問わず必要な情報にアクセスできます。
Officeソフトと連携できるので通話しながら Teams上でExcel資料やPowerPoint資料をメンバーと共同で編集しながら作成する、といったことも可能です。
8-5. Chatwork

出典: https://go.chatwork.com/ja/
Chatworkは2000年に設立されたEC Studioを前身として、2012年に商号変更をして誕生しています。
主なサービスは、ビジネスチャットツールの「Chatwork」の提供です。国産のビジネスチャットツールとしては利用者数No.1です。2022年には登録ID数は500万人を超え、有料プランの利用者だけでも56万人以上です。1対1のチャットだけでなく、グループチャット機能もあり、使い勝手はよいです。
9. 営業・マーケティングソフトのSaaSサービス例
続いて、営業やマーケティング業務に特化したSaaSを紹介します。
9-1. Salesforce

出典: https://www.salesforce.com/jp/
企業が行う営業やマーケティング活動において世界No.1のシェアを誇るSaaSが「Salesforce」というクラウド型のアプリケーションです。
「Salesforce」は、クラウド上で顧客管理や営業管理を行えるSaaS型のアプリケーションで、企業として必要な機能や利用状況に応じて料金を支払うサブスクリプション型のサービスです。
営業部門では、顧客情報や商談内容を管理することで受注率のアップにつなげるサポートができます。例えば見込み客がWeb広告をクリックして、自社との成約に至るまでのプロセスを一覧で確認することも可能です。
また、お問い合わせの内容と顧客情報の確認が1つの画面でできるのでお問い合わせにも迅速に対応できます。例えばコールセンターの顧客対応の内容を効率的に一元管理することなどにも活用されています。
その他にもマーケティングやECサイト運営に役立つさまざまな機能が利用可能です。
9-2. FORCAS

FORCASは、ABM(アカウントベースドマーケティング)を効率化させるためのマーケティングツールです。
アカウントベースドマーケティングは「データをもとにターゲットとなる企業を絞り、そこに営業をしっかりとかけ、売上の最大化を目指す戦略」のことを言います。
FORCASには約150万件以上の企業情報が登録されています。企業はそのデータベースを活用して、ターゲットとなる企業の分析を行うことで、より成約する可能性が高い企業を抽出してリスト化することができます。売上を上げるためには、まずは見込み客を獲得することが必須です。FORCASは、見込み客の獲得に特化した画期的なツールだと言えます。
9-3. Sansan

出典: https://jp.sansan.com/introduction
Sansanは法人向けクラウド名刺管理サービスの「Sansan」を提供する企業です。2007年に設立され「Sansan」を利用する企業は8,000社を超えています。
2012年からは個人向けの名刺管理アプリ「Eight」を開発・提供しています。オフィスの机の中に眠ってしまいがちな名刺は、実は宝の山とも言えます。しかし、もらった名刺を有効活用できずにそのままにしてしまっているパターンは驚くほど多いです。名刺管理サービスを利用することで、自社の資産とも言える名刺から、売上につなげる戦略が立てやすくなります。
9-4. kintone
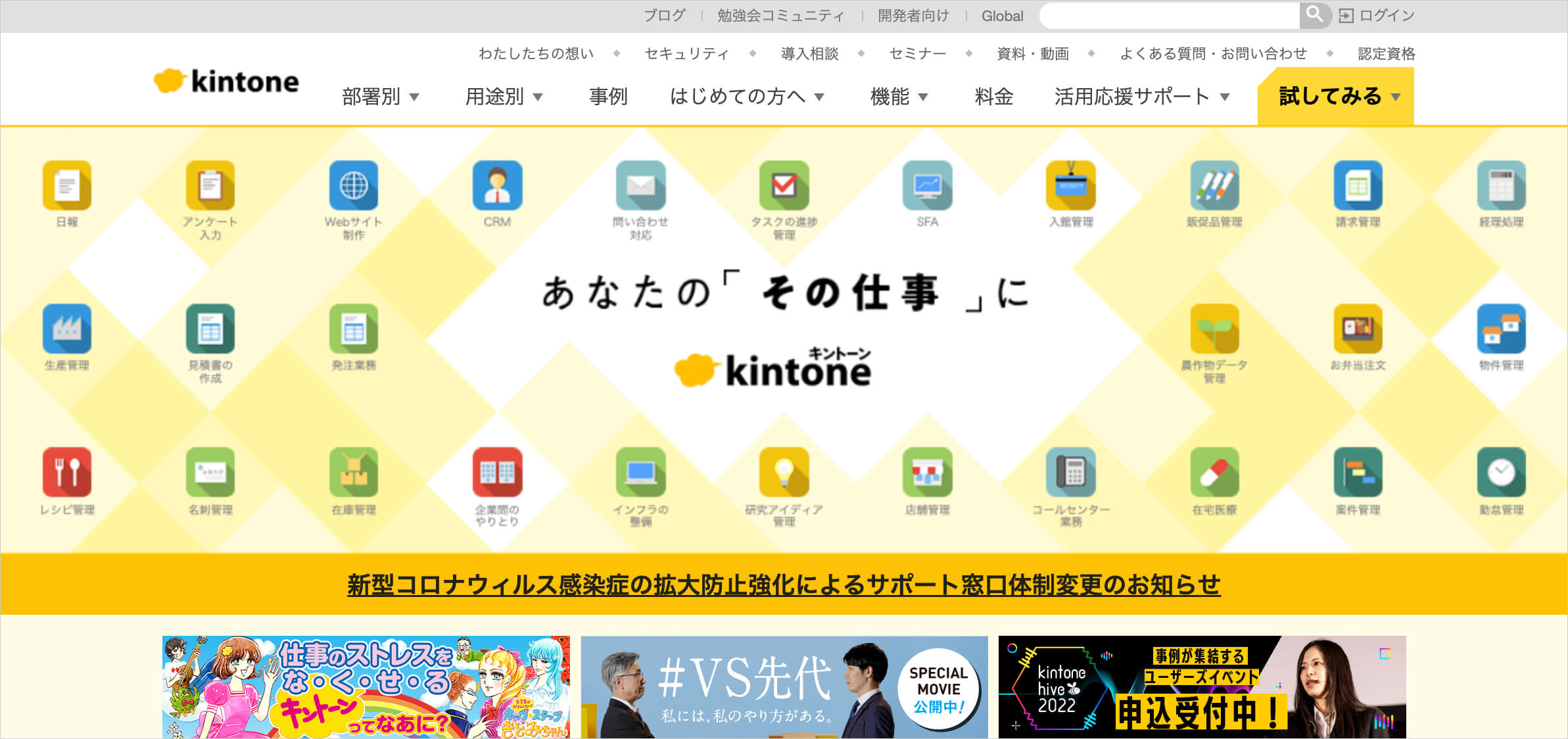
出典: https://kintone.cybozu.co.jp/
Kintoneはサイボウズ社が提供するサービスです。「案件管理」「進捗管理」「日報管理」などのアプリをプログラミング知識がなくても作成可能なサービスです。
サイボウズ社の他製品と連携できるので、既に導入しているサービスがあればおすすめです。テンプレートを組み合わせることで、使いやすくカスタマイズできるので、使い勝手もよいです。
9-5. Zendesk

出典: https://www.zendesk.co.jp/
Zendeskはクラウド型のカスタマーサポートツールです。ヘルプデスクや顧客対応の業務効率化のための機能が豊富に搭載されています。 メールやチャット、電話といったチャネルを問わず、顧客からのすべての問い合わせが集約されるシステムで、顧客対応の担当者の使い勝手が考慮された設計となっています。AIチャットボットと連結させることでオペレーターの負担を減らすことも可能です。
また、LINEや電話対応など、別のツールでの行ったやり取りを顧客ごとに一元管理できますので、問い合わせツールの相違による、担当者間の伝達ミスの予防にもつなげられます。
10. バックオフィス系のSaaSサービス例
つづいて会計や人事といったバックオフィス系のSaaSサービスを紹介します。
10-1. freee

出典: https://www.freee.co.jp/lp/brand/01
2012年7月に設立されたfreeeは、個人事業主やスタートアップ企業といったスモールビジネスから中規模の企業が気軽に利用できる会計ソフトです。データ取込や仕訳を自動化し、経理業務の負担を軽減できるとともに、帳簿・レポートによる経営状況の見える化が可能です。
10-2. マネーフォワード

出典: マネーフォワード
2012年に設立されたマネーフォワードは「お金を前へ。人生をもっと前へ。」をミッションに掲げ、主に個人向けと法人向けの会計アプリを提供しています。
代表的なサービスに個人の家計簿を可視化する「マネーフォワードME」や法人の確定申告や会計業務ができる「マネーフォワード クラウド」があります。「マネーフォワードME」は個人向け家計簿アプリでシェアNo.1となっています。
10-3. 楽楽精算

出典: https://www.rakurakuseisan.jp/lp/contents3
楽楽精算は、中小企業を中心に導入されているクラウド型経費精算システムです。交通費などの経費精算を合理化し、申請者だけでなく経理担当者の負担軽減と企業のコスト削減・生産性向上につなげられます
スマートフォンでいつでもどこでも経費申請できる手軽さが人気です。
ジョルダンの乗換案内を内蔵し、定期区間の控除にも対応しています。
10-4. SmartHR

従業員の情報をデータ化して一元管理できるSaaSサービスです。従業員の雇用契約や入社手続きをはじめ、年末調整に至るまでのさまざまな労務手続きの手間の削減とペーパーレス化が期待できます。
入退社の書類、社会保険・労働保険に必要な手続き書類などを手間なく作成し、管理が可能です。ペーパーレス化に伴い紙の書類を使う手間やコストも削減できます。
10-5. CloudSign

弁護士ドットコムが開発・提供する、導入社数130万社以上、累計送信件数 1000万件超の国内シェアNo1の電子契約サービスです。CloudSignで締結されるすべての契約書・文書には、独自の電子署名がつき、セキュリティが担保されています。紙の文書をインポートできる機能が標準搭載されているため、過去の契約書をスキャン・インポートすれば、電子契約書か文書の契約書かの区別なく一元管理が可能です。
さいごに
今回は、SaaSの基本について解説しました。注目の集まるSaaSですが、 「マーキャリNEXT CAREER」では、上記で紹介したSaaS企業への転職実績があります。ご興味のある方は、ぜひご相談ください。執筆者
マーキャリ 編集部